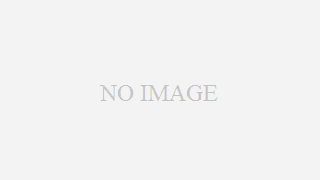 理科
理科 単子葉類と双子葉類の違い|根・茎・葉・維管束の見分け方を図で解説!
単子葉類と双子葉類とは?|はじめに知っておこう!植物にはたくさんの種類がありますが、「葉や茎のつくり」で分類することができます。理科の授業では、「単子葉類(たんしようるい)」と「双子葉類(そうしようるい)」という2つのグループに分けて学びま...
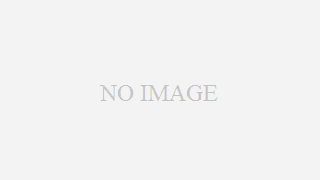 理科
理科 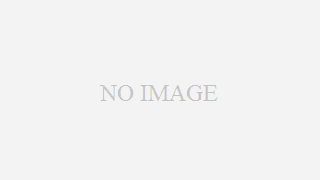 理科
理科 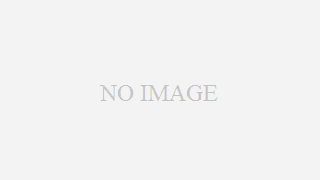 勉強法
勉強法 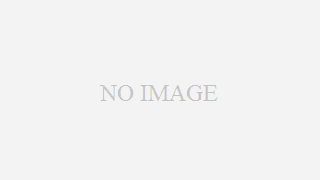 理科
理科 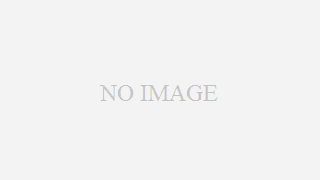 理科
理科 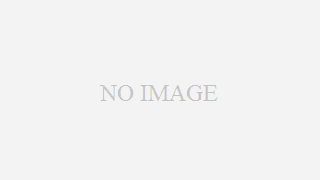 算数
算数 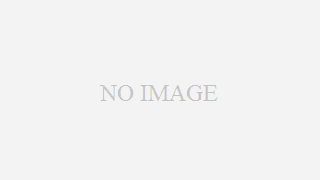 算数
算数 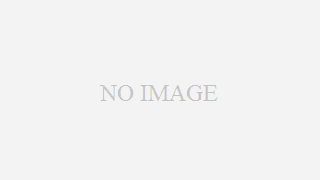 算数
算数 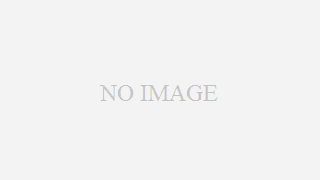 算数
算数 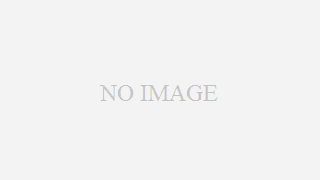 勉強法
勉強法