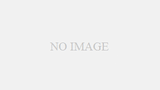中学受験の算数は「基礎固め」がすべて!まず何をすべきか
中学受験の算数を攻略するうえで、最初に必ず意識したいのが 基礎固め です。
難しい特殊算や図形問題ばかりに目が行きがちですが、そもそも計算力や基本的な操作がしっかり身についていなければ、どんなに良い問題集や塾のテキストを使っても成果が出ません。
特に、四則演算や逆算、単位変換などの基本があやふやだと、文章題を読んで式を立てるどころではなく、計算の途中でつまずいて時間切れになってしまうケースが非常に多いのです。
では、具体的にどんな力を小4~小5の早い段階で身につけておくべきなのかを見ていきましょう。
「予習シリーズ」に入る前に必要な算数の力とは
中学受験塾の定番教材ともいえる「予習シリーズ」は、4年生からスタートする子が多いですが、実際のところ 予習シリーズの内容は、小学校でいうと5年生後半~6年生レベルの計算をすでに含んでいます。
たとえば次のような計算力が、予習シリーズに入る前の必須スキルです。
- 分数や小数を含む四則演算を正確かつスピーディーにできる
- 逆算(□を求める計算)が無理なく解ける
- 長さ・面積・体積など、単位の変換が瞬時にできる
これらの計算が反射的にできるようになっているかどうかが、予習シリーズを使いこなせるかどうかの分かれ道になります。
計算が遅いと中学受験の算数が進まない理由
計算が遅い、または正確にできない状態で受験勉強を進めると、子どもも保護者も深刻なストレスを抱えることになります。
その理由は次の通りです。
- 時間が足りない
入試本番は時間との勝負です。典型問題の解法を覚えていても、計算でつまずくと解き切れなくなります。 - 典型パターンの習得に集中できない
受験算数では、特殊算や図形で典型パターンを覚える必要があります。計算が不安だと、思解法習得に集中できません。
実際、予習シリーズの計算問題集には答えしか載っていないことも多く、解き方のプロセスを理解しないまま進めてしまう子も少なくありません。
すると「解けない=算数が苦手」と思い込み、自信をなくしてしまうリスクがあります。
だからこそ、受験算数をスムーズに進めるためには、 基礎の計算力を徹底的に固めることが最優先 なのです。
中学受験の基礎固め|絶対に習得すべき3つの計算
中学受験の算数において、基礎固めと一言でいっても範囲はとても広く感じますよね。
しかし実際は、次の 3つの計算 を確実に身につけておけば、受験勉強はぐっとスムーズになります。
- 四則演算(小数・分数を含む)
- 逆算
- 単位の変換
どれも小学校の範囲内ではあるものの、反復練習なしには定着しにくいポイントです。
それぞれ詳しく解説します。
四則演算(小数・分数を含む)を反射的にできるレベルに
中学受験の算数は、文章題や図形問題のような複雑な問題が注目されがちですが、その解答には必ず 計算力 が土台として必要です。
特に次のような計算を スピード感を持って正確に 解けることが重要です。
- 小数の足し算・引き算・掛け算・割り算
- 分数の足し算・引き算・掛け算・割り算
- 分数と小数の相互変換
たとえば、分数の掛け算で「約分がうまくできない」だけで計算が面倒になり、算数全体が嫌いになる子も多いです。
また、文章題を解く際も、「式は合っているのに計算ミスで不正解」というケースが頻発します。
目標は、計算を いちいち頭で考えなくても手が自然に動くレベル にすること。
そのためには毎日コツコツと計算問題を解き続けるしかありません。
ただし、いきなり難しい問題集をやるのではなく、まずは基礎の計算ドリルから始めるのがおすすめです。
つまずきやすい「逆算」を徹底攻略するポイント
次に重要なのが 逆算 です。
逆算とは、□やxなどの「未知数を求める計算」のことを指します。
- 例:□ × 3 = 24 のとき、□はいくつか?
- 例:分数を含む逆算 □ ÷ (2/3) = 9
この逆算が苦手な子は非常に多く、計算の意味を理解しないまま式をいじろうとして混乱しがちです。
しかし、中学受験の算数では逆算があらゆる単元に登場します。割合、速さ、比、食塩水など…どの分野も 逆算ができないと進めません。
逆算を克服するポイントは次の通りです。
- □を「隠された答え」ととらえ、まず文章を式にする
- 両側を同じ数で割る・掛けるなど、算数のルールを意識する
- 数字を具体的に入れて確認する練習をする
「予習シリーズ」でも逆算は4年生の早い段階から登場しますが、いきなり難しい問題に取り組むのではなく、まずは単純な式を使った逆算問題集で訓練するのが効果的です。
忘れがちな「単位の変換」はどう練習するか
最後に、つい後回しにされがちなのが 単位の変換 です。
しかし中学受験の算数では、単位変換がスムーズにできないと、どんなに問題を解く力があっても失点につながります。
代表的なのは以下の単位変換です。
- 長さ(cm ⇔ m、mm ⇔ cm など)
- 面積(cm² ⇔ m² など)
- 体積(cm³ ⇔ m³、L ⇔ mL など)
- 重さ(g ⇔ kg など)
- 時間(分 ⇔ 時間、秒 ⇔ 分 など)
特に面積・体積の換算は 1桁違いの計算ミス が起こりやすいため要注意です。
例えば、
- 1 m² = 10,000 cm²
- 1 m³ = 1,000,000 cm³
これらを覚えていないと、大問全体を間違えるリスクすらあります。
単位変換を身につけるコツは以下の通り。
- 基本の換算表を目に見えるところに貼る
- 暗唱する習慣をつける
- 簡単な問題を毎日少しずつ解く
たった1問でもいいので、毎日単位変換の問題を解くことが定着への近道です。
そして、基礎が固まったら「予習シリーズ」の計算問題集で実戦的な演習に進むと良いでしょう。
以上が、中学受験の基礎固めとして 絶対に外せない3つの計算 です。
これらをマスターすることで、受験算数の本格的な学習に安心して入っていけます。
基礎計算を鍛える!おすすめ問題集と使い方
「中学受験の算数は基礎が大事」とわかっていても、
「じゃあどんな問題集を使えばいいの?」
と迷われる保護者の方は多いと思います。
実際、塾で配られる計算問題集だけでは難しすぎて、
「全然できない…」とお子さんが苦手意識を持ってしまうケースも珍しくありません。
ここでは、計算の「基礎の基礎」から始めたい方向けの問題集や、
塾用問題集を使う際の注意点、そして問題集を繰り返すコツをご紹介します。
「基礎の基礎」から始めたい人向けの問題集
もし計算が苦手なお子さんの場合、いきなり塾用教材に取り組むのはハードルが高いです。
そこでおすすめなのが、より基礎的な市販の計算ドリルや問題集です。
例えば、次のような問題集が「基礎の基礎」にぴったりです。
✅ くもんの小学ドリル 計算シリーズ
- とにかく問題量が豊富で、反復練習に最適。
- 難易度が段階的に上がるため、つまずきにくい。
✅ 陰山英男の徹底反復シリーズ
- 毎日決まった量を短時間でやる設計。
- 数字の書き方やスピードも意識できる。
これらの問題集は、受験用教材より解説が詳しく、保護者の方が家庭で教える際にも使いやすいのがメリットです。
「計算が遅い」「すぐミスする」という場合は、まずこれらでしっかり反復練習することをおすすめします。
予習シリーズ計算問題集を使うときの注意点
多くの塾で使われている 予習シリーズ 計算問題集 は、中学受験を本格的に目指す子には欠かせない教材です。
しかし、使い方を間違えると、ただの「答え写しノート」になりかねません。
予習シリーズ計算問題集の注意点
- 解答が答えしか載っていない
→ 計算過程を書かないと「なぜ間違えたか」が分からず、復習ができない。 - 問題数が多く、時間的に負担になりやすい
→ 最初から全ページやろうとせず、苦手な範囲を絞るのがおすすめ。 - 難易度が高め
→ 基礎ができていないと、解けなくてやる気を失うリスクが高い。
予習シリーズを使うときは、以下のポイントを意識しましょう。
✅ 答え合わせの際、必ず計算式を書き残す
✅ 間違えた問題には「×」を付けて、再度解き直す
✅ どうしても分からない場合は、基礎問題集に戻る勇気を持つ
「間違い直しノート」を作り、同じ間違いを繰り返さない仕組みにするのも非常に効果的です。
問題集を繰り返す効果的な勉強法
基礎固めで最も大切なのは、繰り返し解くこと です。
しかし、ただ漫然と繰り返すだけでは力はつきません。
次のように、やり方を工夫するのがポイントです。
効果的な繰り返しの方法
✅ 間違えた問題を必ずリスト化する
→ 間違いノートを作り、解き直す回数を記録する。
✅ 正解した問題は次回は飛ばす
→ 全問やり直しは効率が悪い。弱点だけを重点的に。
✅ タイムを計る
→ 計算はスピードも重要。時間を意識するだけで集中力が増す。
✅ 小さな目標を設定する
→ 「今日は10問だけ完璧にする」といった短期ゴールがやる気を保つ。
特に計算は「手が勝手に動く」くらいの反復が必要です。
時間が許す限り、間違えた問題だけは3回以上解き直すようにすると、確実に定着していきます。
計算力は中学受験算数の土台です。
基礎の計算問題集からスタートし、徐々に予習シリーズのような応用教材へステップアップすることで、
「塾の授業についていけない」という不安も解消されるはずです。
受験算数の基礎固め|計算力を土台に典型パターンを攻略する方法
計算力が身についてきたら、いよいよ本格的な中学受験算数の世界に入っていきます。
ただし、ここから先に進むときに大切なのは、やみくもに問題を解きまくることではありません。
受験算数にはいわゆる 「典型パターン」 というものが存在します。
つまり、頻出の出題パターンや解法の型があり、それを知っているかどうかが合否を左右するのです。
ここでは、典型パターンを攻略するために絶対に意識してほしいポイントをお伝えします。
「問題を解くのに必要な知識」を意識する
受験算数では、ただ計算を速く正確にこなすだけでは勝負になりません。
文章題や図形問題には必ず「解くための知識」が存在するからです。
例えば、以下のような知識です。
- 割合・比・速さの基本公式
- 濃度計算の基本パターン
- 規則性を見抜くための着眼点
- 平均やつるかめ算の解き方の型
この「問題を解くのに必要な知識」を最初から全部覚えようとするのは大変ですが、問題を解きながらポイントを少しずつ蓄積していくことが重要 です。
例えば:
- 「速さ=道のり÷時間」は絶対に暗記
- 食塩水の問題では「全体の量×濃度=食塩の量」と意識する
- 割合の問題は線分図を使うと整理しやすい
お子さんに「どうしてその式を立てたの?」と質問してみて、自分の言葉で説明できるか 確かめるのもおすすめです。
文章題攻略に必須!線分図・面積図・てんびん図を描く習慣
「文章題になると急に解けない」というお悩みは非常に多いです。
その大きな原因の一つが、頭の中だけで整理しようとして混乱してしまうこと。
そこで絶対に身につけてほしいのが、図を描いて考える習慣 です。
具体的には以下の3つが特に重要です。
✅ 線分図
- 割合、比、つるかめ算などで活躍
- 数量の関係がひと目でわかる
✅ 面積図
- 割合や平均、速さの問題で便利
- 足し算・引き算の関係を整理できる
✅ てんびん図
- 濃度や平均算に最適
- 全体のバランスを視覚化できる
例えば、つるかめ算の文章題を読んだときも、線分図を描いて
「全体の個数」「差」「合計金額」などを整理すれば、式を立てるハードルがぐっと下がります。
「うちの子は図を描くのが面倒だと言うんです」というご相談もよくありますが、
図を描かずに頭の中だけで解けるようになるのは受験直前期の話 です。
基礎固めの時期は、むしろ どんなに簡単な問題でも必ず図を描くこと を習慣にするのが合格への近道です。
塾テキストが難しいときにおすすめの参考書
塾の授業を聞いていても
「よくわからないまま家に帰ってきた」
というお子さんは少なくありません。
そんなときに助けになるのが、解説がとても分かりやすい市販の参考書や問題集です。
特におすすめなのが次の2冊です。
塾技100
✅ 塾技100(文英堂)
- 中学受験で頻出の典型問題を100の「技」にまとめた本
- 1つの技ごとに、例題→ポイント解説→類題 という流れで学べる
- 図や式の書き方も非常に丁寧
- 苦手単元のピンポイント復習に最適
塾技100は「解法のパターン集」として非常に優秀です。
塾で習った内容がよく分からなかったとき、塾技で該当する技を探すと 別の説明で理解できることが多い ので、受験生必携の一冊といえます。
魔法ワザシリーズ
✅ 中学受験 魔法ワザシリーズ(文英堂)
- 各単元ごとに解き方のコツを「魔法ワザ」として紹介
- 言葉が平易で、小学生にもわかりやすい
- イラストや図が多く、視覚的に理解しやすい
例えば「中学受験 算数 魔法ワザ図形」「魔法ワザ割合・比」など、単元別に出版されています。
塾のテキストが難しすぎるとき、魔法ワザシリーズを読ませると 「あ、そういうことだったんだ!」 と理解が進む子は本当に多いです。
塾テキストが難しく感じるのは、解説が少なすぎるか、専門用語が多いから というケースがほとんどです。
市販の解説書をうまく併用することで、苦手単元の壁を突破できます。
典型パターンを覚え、計算力を活かして解法を素早く使いこなすこと。
これが「受験算数の基礎固め」の完成形です。
基礎固めを確実にする!復習のコツ
基礎固めで一番大切なのは、「やりっぱなしにしないこと」 です。
せっかく問題を解いても、間違えたところを放置してしまうと、結局また同じところでつまずきます。
特に中学受験の算数は範囲が広いため、計画的に復習する仕組みを作ることが合格への大きなカギになります。
ここでは、計算や典型パターンの復習を効率よく進めるためのコツをご紹介します。
計算は「できるまでやる」が基本
計算に関しては、「間違えたけど次に進もう」 というやり方は絶対にNGです。
なぜなら、同じような問題が再び出たとき、必ずまた間違えるからです。
計算問題の復習の基本は 「できるまでやる」 という姿勢。
次のような方法をおすすめします。
✅ 間違えた問題にマークをつける
- 「×」印を問題番号の横に必ず書いておく
✅ 翌日もう一度解く
- できなかったら、さらに翌日に再チャレンジ
✅ 正解したらチェックを外す
- 正解できた問題は繰り返す必要なし
計算力はスポーツと同じで、頭で覚えるものではなく 体に染み込ませるもの です。
計算だけは「できるまで繰り返す」のが鉄則です。
典型パターンの復習は「3回」を目安に
受験算数の典型問題は、一度解いただけでは定着しにくいものが多いです。
そのため、「復習の回数」を決めておくことがとても重要 です。
おすすめは 「3回」 の復習を目安にすること。
- 1回目:初見で解く → 間違えた問題をチェック
- 2回目:数日後に再チャレンジ → まだ解けない問題をさらに絞り込む
- 3回目:さらに間隔をあけて確認 → 完璧にする
特に文章題や図形問題は、解き方を忘れやすいので、3回くらい同じ問題に取り組むことで知識が定着します。
「3回も同じ問題をやるなんて時間がもったいない」と感じる方もいるかもしれませんが、新しい問題ばかりに手を出すより、過去に間違えた問題を完璧にする方が確実に成績アップにつながります。
わからない問題をいつ切り捨てるかの判断基準
復習は大切ですが、すべての問題を完璧にする必要はありません。
中学受験は範囲が非常に広いため、「切り捨てる勇気」 も同じくらい大切です。
特に次のような問題は、無理に粘りすぎない方が良いことが多いです。
✅ 何度解き直してもまったく理解できない問題
✅ 解き方を読んでもピンとこない難問
✅ 入試でほとんど出題されない特殊な問題
目安としては、「3回解き直してもダメなら一旦保留」 にするのがおすすめです。
保護者の方がやりがちなのは、
「どうしてもこの問題を解けるようにさせたい!」
とお子さんを追い込んでしまうこと。
でもそれを続けると、お子さんが算数そのものに苦手意識を持ってしまうリスクが高いです。
むしろ、
「これは今は飛ばそう。また余裕ができたら戻ろう。」
と伝えてあげる方が、精神的にも良い結果につながります。
大事なのは、受験に必要な基礎と典型パターンを確実に身につけること です。
全部を完璧にしようとするより、優先順位をつける方が合格への近道になります。
中学受験は時間との勝負でもあります。
計算は「できるまで繰り返す」、典型パターンは「3回解き直す」、そして「切り捨てる問題は思い切って保留にする」。
このメリハリのある復習こそが、基礎固めを確実にし、合格へ導いてくれます。
まとめ|中学受験算数の基礎固めを制する者が合格を制す
中学受験の算数と聞くと、特殊算や難しい図形問題など、華やかなテクニックばかりに目が行きがちです。
しかし、実際に合格を勝ち取るお子さんたちに共通しているのは、基礎計算が完璧に身についていること です。
どんなに難易度が高い問題でも、解答の最後は必ず計算力がものをいいます。
また、計算が早く正確にできることで、応用問題に時間を残せるため、試験本番で大きなアドバンテージになります。
計算力を磨いて余裕を持って中学受験に臨もう
今回お伝えしたように、中学受験算数の基礎固めには次のステップが欠かせません。
- 小数・分数を含む四則演算を反射的に解けるようにする
- 逆算をしっかり理解し、自在に使いこなせるようにする
- 単位の変換を確実にマスターする
- 基礎計算ができたら、典型パターンを徹底的に身につける
- 間違えた問題を放置せず、繰り返し復習する
これらをコツコツ積み上げれば、必ず算数に対する自信がつきます。
自信がつけば、塾の授業にもついていけるようになり、さらに成績が伸びるという好循環が生まれます。
お子さんの算数が伸び悩んでいると感じたら、ぜひ一度立ち止まり、基礎の基礎からやり直す勇気 を持ってください。
それこそが、遠回りのようでいて一番の近道です。
基礎固めを制する者が、中学受験を制します。
ぜひ、お子さんと一緒に一歩ずつ進んでいきましょう!