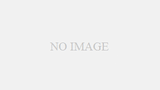中学受験は小学生にとって大きな挑戦です。そのスタート地点である小学4年生では、どんな勉強を進めるべきなのでしょうか?
この記事では、受験勉強の土台となる「計算」「漢字・ことわざ・慣用句」の習得と、それに伴う学習習慣の大切さについて解説します。また、読書の大切さについても触れます。
計算と漢字は、ほぼ毎日取り組む
「計算」と「漢字」は、週4日以上、1日5~15分の練習が理想です。これは単にスキルを習得するためではなく、学習習慣を身につけることも目的の一つです。
なぜ、ほぼ毎日やるのか?
受験指導塾では、計算や漢字の練習を前提として授業が進みます。つまり、これらを塾に頼り切るのは難しいのです。
特に計算や漢字は繰り返しの練習が必要であり、「週に2回の指導」では追いつきません。自宅で継続的に取り組むことで、自然と学ぶ力が育ちます。
解きっぱなしにしない工夫
練習後の〇付けは必須です。子どもに任せっきりにすると、適当に済ませてしまったり、最悪の場合はやらないこともあります。
保護者が監視するか、忙しい場合は家庭教師や塾を活用しましょう。費用はかかりますが、計算と漢字は「ほぼ毎日手を動かすべき内容」ですので、正確な学習管理が必要です。
計算力の重要性「四則演算と単位の変換」
中学受験の学習を進める上で、計算力は基礎中の基礎です。特に四則演算と単位の変換は、スムーズにできるようになるまで徹底的に練習しましょう。
計算や単位の変換に手間取っていると、問題を解く時間が不足します。計算に悩むことで、せっかく学んだ解法が使えなくなるケースも多いのです。土台がしっかりしていないと、5年生・6年生の本格的な学習についていけなくなります。
漢字・ことわざ・慣用句の習得
小学生は語彙力が十分ではないため、意識的に漢字、ことわざ、慣用句を覚える必要があります。これらの語彙力が不足していると、問題文の意味を正確に読み取ることができません。
国語の読解問題で使われている表現が理解できないため、文章を根気強く読む習慣が身に付きません。それが算数や理科の問題文でも同じ障害となるのです。
受験算数4年生の内容は、後回しにしてもOK
「中学受験は4年生から始めるべき」とよく言われますが、実際には計算、漢字、学習習慣といった基礎ができていれば5年生からでも十分間に合います。
小4で習う内容はカバー可能
たしかに、小4では弁償算(つるかめ算の応用)などの難易度の高い問題も出てきます。しかし、計算・漢字練習の学習習慣ができていないのに、難しい問題に取り組んでも習得できないと思います。
毎日コツコツ勉強する習慣ができれば、小5から集中して取り組むことで十分に追いつけます。そのため、計算や漢字練習を通した学習習慣をつくるのを優先するべきです。
もちろん、今のうちから取り組むことができる(理解することができる)文章問題、図形の問題はやっておくほうががいいです。ただし、難しいと思ったら無理をせず、計算などの基礎を徹底しましょう。
4年生での最大の課題「学習習慣をつくる」
受験勉強のスタートが遅くても、学習習慣が身についていれば大きな問題はありません。しかし、早い段階で始めたとしても、習慣がなければ学びが定着せず苦労します。まずは毎日の学習を習慣化しましょう。
読書を取り入れる
可能であれば、1日10分でも読書を取り入れることをおすすめします。
読解力アップに繋がる読書の効果
読書をすることで、漢字、接続詞、指示語、慣用句、比喩などに触れる機会が増え、自然と読解力が向上します。また、国語の読解問題を解く際の基礎力が強化されます。
どんな本を読むべきか
特に読みたい本がなければ、説明文がおすすめです。指示語、接続語の使い方を身に付けられます。また筆者の主張が読み取りやすいです。岩波ジュニア新書が読みやすいと思いますが、難しければ他のでもいいです。「小4 読書 おすすめの本」と検索して適した本を見つけてもいいですね。
注意点
読書にはまりすぎて勉強をサボらないように注意しましょう。また、読み飛ばしは避け、精読を心がけることが大切です。精読を重ねることで、読むスピードも徐々に上がり、読解力も強化されます。
まとめ
中学受験を成功させるためには、小4の段階で計算力と漢字力を鍛え、学習習慣を身につけることが欠かせません。また、これらに加えて読書を取り入れることで、さらに力を伸ばすことができます。
受験勉強の本格的なスタートは小5からでも間に合いますが、そのためには今のうちに計算、漢字、読書といった土台をしっかりと築いておきましょう。