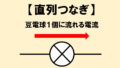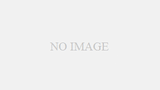心臓のつくりを4つの部屋で覚えよう!

心臓は、私たちの体の中にある「ポンプ」のような働きをする大切な器官です。血液を全身に送り出したり、戻ってきた血液を受け取ったりしています。
そんな心臓は、「4つの部屋」に分かれています。この4つの部屋の名前と働きを覚えることで、血液の流れがとてもわかりやすくなります。
4つの部屋とは?
心臓には、右側に2つ、左側に2つ、合わせて4つの部屋があります。
- 右心房
体中をめぐってきた血液が、いったん戻ってくる場所です。この血液は酸素が少なく、二酸化炭素をたくさんふくんでいます。 - 右心室
右心房から流れてきた血液を、今度は肺へ送り出します。肺では、二酸化炭素を出して、酸素を取り入れます。 - 左心房
肺で酸素をたっぷり受け取った血液が戻ってくる場所です。さっきまで二酸化炭素が多かった血液が、ここで元気を取り戻します。 - 左心室
酸素をたっぷりふくんだ血液を、全身にむかって力強く送り出します。
なぜ左心室の壁は厚いの?
4つの部屋の中でも、左心室の壁は特に厚くて、筋肉がとても発達しています。それは、全身に血液を送り出すには強い力が必要だからです。
遠くは足の先や頭のてっぺんまで血液を送らなければなりません。そのため、他の部屋よりもしっかりとした筋肉がついているのです。
まとめ
心臓のはたらきを覚えるときは、「右から肺へ、左から全身へ」と覚えると便利です。
- 体 → 右心房 → 右心室 → 肺
- 肺 → 左心房 → 左心室 → 体
この順番をイメージしながら、心臓の4つの部屋をしっかり覚えておきましょう。
動脈と静脈ってどう違うの?

血管には、いくつか種類がありますが、この章では「動脈(どうみゃく)」と「静脈(じょうみゃく)」について解説します。それぞれに大切な役わりがあり、つくりや流れる血液の向きもちがいます。
動脈とは?〜血液が出ていく血管〜
動脈は、心臓から血液が出ていくときに通る血管です。たとえば、心臓の左心室から全身へ送り出される血液は、「大動脈(だいどうみゃく)」という太い動脈を通って流れていきます。
動脈の特徴は、血液を強い力で送り出す必要があるため、血管の壁がとても厚くてしっかりしていることです。
静脈とは?〜血液がもどってくる血管〜
静脈は、体のすみずみから心臓へ血液をもどすときに通る血管です。たとえば、足の先から戻ってくる血液は、長い道のりを通って心臓に帰ってきます。
でも、ここで1つ問題があります。血液は重力にさからって上にのぼってこなければならないので、逆流(さかのぼって戻ってしまうこと)しない工夫が必要です。
そのために、静脈の中には「弁(べん)」と呼ばれる小さなフタのようなものがついています。弁は一方向にだけ開いて、逆流を防いでくれます。
動脈と静脈のちがいのまとめ
- 動脈
心臓から出ていく血液が流れる血管。
血管の壁が厚い。 - 静脈
心臓へもどる血液が流れる血管。
弁がある。
動脈血と静脈血のちがいをおさえよう!
前の章で、「動脈」と「静脈」という血管のちがいを学びました。でも、「動脈を流れる血液=動脈血」「静脈を流れる血液=静脈血」というわけではありません。
ここでは、動脈血(どうみゃくけつ)と静脈血(じょうみゃくけつ)のちがいについてしっかり覚えましょう!
動脈血とは?〜酸素が多い血液〜
動脈血は、酸素(さんそ)をたくさんふくんだ血液です。この血液は、肺で酸素を受け取ったあと、心臓の左心房 → 左心室 → 大動脈を通って全身へと運ばれます。
酸素は、私たちの体の細胞が元気に働くために必要なエネルギーを作るのに欠かせません。そのため、動脈血はとても大切な役わりを持っています。
静脈血とは?〜二酸化炭素をたくさんふくんだ血液〜
静脈血は、二酸化炭素(にさんかたんそ)を多くふくんだ血液です。体の細胞が活動するときに出す「ゴミ」のようなものが二酸化炭素です。
この静脈血は、全身から右心房 → 右心室 → 肺動脈を通って肺へと送られます。肺ではこの二酸化炭素を外に出し、代わりに新しい酸素を取り入れます。
ポイント:動脈=動脈血?静脈=静脈血?いいえ、ちがいます!
ここがとても大事なポイントです。
多くの人がまちがえやすいのですが、「動脈=動脈血」「静脈=静脈血」とは限りません。
- 肺動脈(はいどうみゃく)
名前は「動脈」ですが、実は中を流れているのは静脈血(二酸化炭素が多い血液)です。なぜなら、肺に向かう途中だからです。 - 肺静脈(はいじょうみゃく)
名前は「静脈」でも、流れているのは動脈血(酸素が多い血液)です。肺で酸素を受け取ったあとの血液だからですね。
つまり、「どの血管を流れているか」ではなく、「どんな成分をふくんだ血液か」で、動脈血・静脈血は分けられます。
- 動脈血
酸素が多い血液 - 静脈血
二酸化炭素が多い血液
体の左半分は酸素が多い血液が流れていて、右半分は二酸化炭素が多い血液が流れている。
そのなかでも、特に酸素が多いのが肺静脈であり、二酸化炭素が多いのが肺動脈だ。
このように、「動脈を流れるから動脈血」というわけではない。その点には注意しておこう。
左と右で流れる血液のちがい
心臓を中心にして考えると、左側(左心房・左心室)には酸素が多い動脈血が流れ、右側(右心房・右心室)には二酸化炭素が多い静脈血が流れています。
これをイメージで覚えておくと、テストでもまちがえにくくなりますよ!
まとめ:「心臓」と「血液の流れ」を3つのブロックでおぼえよう!
ここまで読んでくれたみなさん、ありがとう!
最後に、血液の流れや心臓のはたらきを覚えるときのコツをもう一度おさらいしましょう。
この4つのブロックに分けて覚えることで、テストでも自信をもって答えられるようになりますよ!
- 心臓のつくり(4つの部屋)
右心房、右心室、左心房、左心室。それぞれの出入り口をしっかり覚えよう! - 動脈と静脈のちがい
心臓から出るのが動脈、もどるのが静脈。血管のつくりもポイント。 - 動脈血と静脈血
酸素の量で決まる。名前と中身がちがう「肺動脈・肺静脈」に注意!